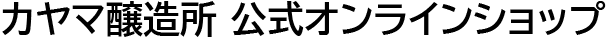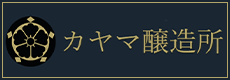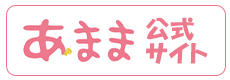- TOP
- BLOG
2021/04/05 17:18
日本酒工程その①では、お酒を造る工程を見ていきました。
今回は、その工程をもう少し詳細に案内します。
日本酒は「一麹、二酛、三造」で造られると言われます。
その第一工程麹造りから見ていきましょう~!
① 精米
お酒を造るためにはお酒にふさわしいお米=酒米が必要です。
酒米は食用米とは違い、コシヒカリのような粘り気があって柔らかい米は酒米には向きません。
反対にバサバサして硬く、そのまま食べると食用に向かないまずいものです。
食用米をそのまま使うと、粘りで固まり麹菌が広がりません。
酒米の品種は山田錦を筆頭に、五百万石、美山錦等102種あるそうです。
酒米は食用のお米に比べて栽培が難しく、筆頭に挙げた山田錦は晩生のため台風の被害を受けやすく、害虫にも弱いため多品種より栽培しにくいと言われます。
酒米を選んだあとの精米では、米の外側の「雑味」の元になるタンパク質を落とします。
ここで、お米を削ります。その削り具合は「精米歩合」と呼びます。
お米をたくさん削ると精米歩合は低くなります。
「磨き二割三分」といういい方をしますが、これは精米歩合23%のことで100gの玄米の内23g残ったものが精米ということになります。
吟醸酒は60%以下、大吟醸酒は50%以下の精米歩合です。
精米後、摩擦で熱くなった米は摩擦熱を放散させる「枯らし」の後に、水洗いをします。

② 洗米
浸水、浸清ともいい、米についている糠を落し、米に水分を含ませます。
水に浸けて、芯まで適度に吸収させます。
米の品種や新米・古米、作付の条件等の違いがあるので、汲水にはその都度調整が必要なので手作業になります。
米が水を吸い過ぎると蒸米が柔らかくなり、また精米歩合が低くなるとほど吸収速度が速くなるので、絶えずチェック・調整するという手間がかかる事になります。
③ 蒸し
浸けた白米は蒸籠で蒸します。家庭で作られていたどぶろくは、炊いたお米を
いますが、蒸した酒米は炊き米に比べ硬めに仕上がり、個々の米粒の表面積が大きくなることで麹の付き面積が広がり、糖化と発酵のバランスが良い平行複発酵する結果をもたらします。
炊いたお米の水分は約65%、蒸した酒米は35%で、麹菌の繁殖に最も適した水分量は35~40%と言われています。

④ 麹造り
蒸米は麹室(こうじむろ)で、30度ぐらいに冷やした蒸米に種麹を掛けて麹造をします。
麹づくりが日本酒つくりの命で、麹の出来具合で酛(酒母)や造り(醪)の出来が決まり、酒の品質が決まります。
そのため麹菌の増殖が始まると体力勝負と言われるように寝ずの番が続きます。
ここまでの麹造りで、酒米から様々な発酵成分が作られ、次のアルコール醸成の条件を造るのですが、栄養成分の元になる甘酒はここまでの過程で作られています。

<豆知識>
麹室に入る杜氏(とうじ)や蔵人には納豆は厳禁です。蔵を見学する人にも納豆を食べたり持ち込まないという禁句が掲示されますが、納豆菌は汚染力・繁殖力が強く100度で熱湯消毒しても死滅しないのです。